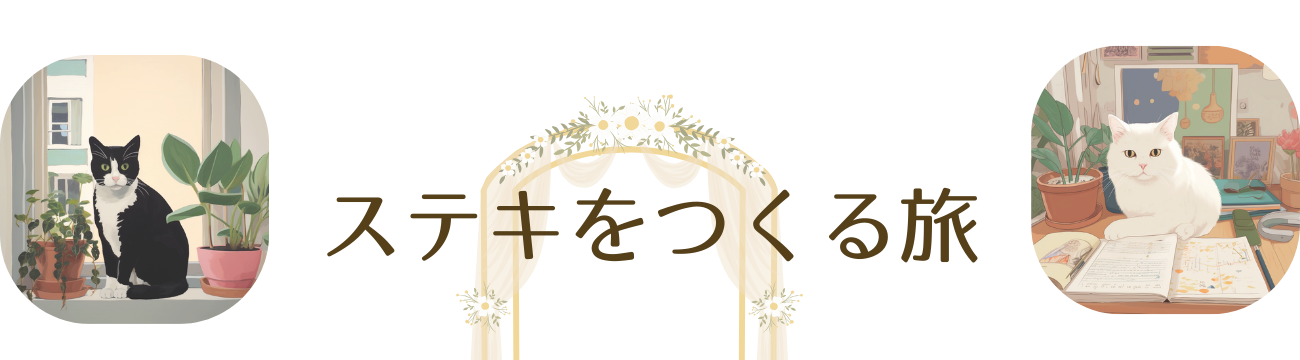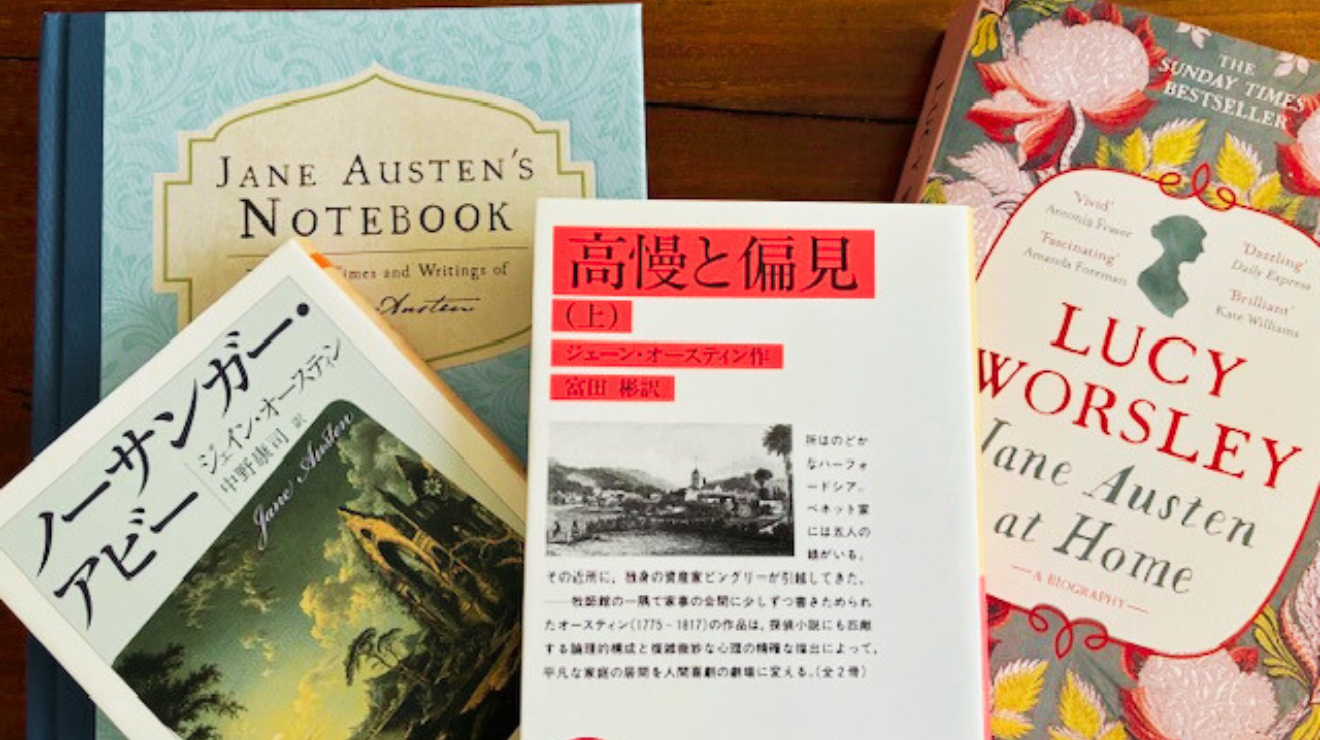原田マハさんが連れて行ってくれるゴッホの世界ー3作品

原田マハさんと言えば、アート作品を題材にした小説が面白いですよね。その小説を読むと、知らず知らずのうちにアートの世界に引き込まれていき、名画を見た後のように満たされた気持ちになっているのです。
そんな原田マハさんの作品の中から、今回はフィンセント・ファン・ゴッホについて書かれた作品3つをあげて、ゴッホの世界を一緒に訪れて見たいと思います。
1 原田マハさんのアート小説の魅力
まず作品を紹介する前に、原田マハさんのアートを題材にした小説の魅力について語らせてください。
原田マハさんの作品に出会う前も、ゴッホについての解説は何度も目にしたことがありました。
生きている間には才能を認められず、自殺してしまった、精神を病んで耳を切った、フランスのアルルやサン=レミで過ごしたことがあった、これらの情報はどれも断片的な事実であり、ゴッホという人物像が私の中で繋がっていませんでした。
しかし、原田マハさんの3作を読んで、ゴッホという人物のストーリーがスッと頭の中に入ってきたのです。そして、ゴッホがとても愛おしく思える存在となったのです。
マハさんの小説では、画家の解説本で得る知識とは違い、画家その人の人生をストーリーとして味わえるところが魅力なのです。
では具体的な作品を取り上げて、見ていきましょう。
2 原田マハ『たゆたえども沈まず』
この小説は、1962年のゴッホの命日、ゴッホが最期を遂げたオーヴェール=シュル=オワーズが舞台となって始まります。この冒頭で登場する人物の重要性、そして「たゆたえども沈まず」というの言葉の大切さは、本を読み終えて再度冒頭を振り返ることで重みがまします。
そして、時代は遡り1886年、舞台はパリへと移ります。当時ヨーロッパで人気が広まっていた浮世絵を中心に、パリで日本の芸術作品を扱う画廊を営む林忠正と、忠正に呼ばれて後からやってきた、画廊を手伝う後輩の加納重吉の話が描かれています。そしてそこには、同じくパリの画廊で働くゴッホの弟テオも登場します。そこにあのフィンセント・ファン・ゴッホが突如現れ、ストーリーは展開していきます。
ゴッホもかつてはテオと同じように画廊で働いていましたが、商売人として働くことが不向きであったゴッホは、やがて自ら画家を目指すようになりました。そして、そんな兄フィンセントの生活費まで工面しつつ、兄の才能を信じてテオはゴッホとパリで一緒に暮らしはじめます。
テオが画廊で働いているのだから、そこで兄フィンセントの絵を売ればいいではないか、と思いたいところなのですが、それは無理だったのです。当時のパリではアカデミズム絵画が主流、新興画家の一派として印象派と呼ばれる画家たちが活動しはじめていましたが、テオが勤めている画廊「グーピル商会」では、印象派の絵画は全く芸術的価値を認められていなかったのです。
そしてその頃、パリでは日本の浮世絵が人気を集めていました。印象派の画家と浮世絵は、鮮やかな色彩を使った自由な作品でした。それは、保守的なサロンでは描かれない「新しい絵画」だったのです。そして、ゴッホが描く絵画にもまた、心に訴える素晴らしいものがあったのですが、世間ではそれはまだ良い作品として評価されるものではなかったのです。そして、ゴッホの作品が受け入れられるようになった時には、すでにゴッホはこの世を去っていたのです。
自分の作品が認められずに苦しむ兄、兄の絵を信じて応援する弟、この2人の生活を読んでいると、時に苦しくやるせない気持ちになります。
浮世絵を愛したゴッホは、日本への憧れを募らせ、林忠正に日本へ連れて行って欲しいと頼みます。そんなゴッホに忠正は、このフランスで芸術の理想郷(ユートピア)、自分の日本をみつけるのだと言い、ゴッホへアルル行きを勧めます。
アルルで創作活動に打ち込むゴッホでしたが、ゴッホには仲間が必要だったのです。そこで、ゴーギャンにゴッホの仲間としてアルルでの活動することを勧めます。アルルへ行く費用の工面とそこで制作される作品を買い取るというテオとの約束のもと、ゴーギャンはアルルにいるゴッホの元へ旅立ったのです。2人はそこで互いに素晴らしい作品を残しますが、やがて仲違いをし、ゴーギャンはアルルを去ることにしたのです。そして、その時ゴッホは自らの耳を切ったのです。
この場面では、ゴッホの苦悩と共に、テオの苦悩も描かれています。テオが同郷の女性ヨーと出会い、まさに結婚を進めていた時の出来事だったのです。その後、ヨーと結婚したテオと兄フィンセントとの共同生活が再開されることはありませんでした。
ゴッホは、アルルからサン=レミの療養所へ移り、そこで創作活動を続けます。
そこで、『星月夜』や『糸杉と星の見える道』などの名作が描かれます。ゴッホが描いた作品は、すぐにテオの元へ届けられており、テオの家にはゴッホの絵が画廊のように飾られていました。そして、テオの妻となったヨーもまた、ゴッホの絵を愛していたのです。
それから、ゴッホは自らも画家であるガシェ医師がいるオーヴェール=シュル=オワーズへの移住を決意します。移住の前、3日間だけパリのテオの元を訪れます。その時には、テオとヨーの1人息子であるゴッホと同名のフィンセントも誕生していました。
オーヴェール=シュル=オワーズでは『医師ガシェ』の肖像や『オーヴェルの教会』などの作品を残しますが、ゴッホはこの地でピストルで自らの腹を撃ち、3日後に命を落としました。自らに向けて発砲したとの知らせを聞いたテオは、すぐに兄フィンセントのところに駆けつけ、最後に言葉を交わします。
アルルでゴッホが耳を切った時も、ゴッホの葬儀の時も、小説の中でテオのそばには重吉がいました。この加納重吉とは、実際には存在しないフィクションの人物です。けれど、原田マハさんのこの小説の中で、重吉はテオとゴッホのそばで2人を見つめ、テオを支える友人として欠かせない存在となっています。
作品の中には、このタイトルである「たゆたえども沈まず」という言葉が何度か出てきます。それは、ゴッホが描きたかったものであり、この小説に登場する、パリで画廊を開いていた日本人林忠正の生き方、そして思いでもあるのです。パリの町を流れるセーヌ川。時代が変わっても川の流れは変わらない。そこに浮かぶ船のように、たゆたえども、沈まずに生きていく。
林忠正とゴッホは実際このように親しかったのでしょうか。
いいえ、残念なことにこれは小説の中でのお話です。原田マハさんが林忠正をここに登場させた思いが、次に紹介する作品の中に描かれていました。
3 原田マハ『ゴッホのあしあと』
『たゆたえども沈まず』は、幻冬社の雑誌パピルスで連載されていました。そして、連載を終えた2017年10月に、原田マハさんは再びフランスのゴッホに会いに行きました。ゴッホゆかりの地を歩いて、ゴッホ兄弟と林忠正に、小説ができたことを報告するために。
この本『ゴッホのあしあと』は小説ではありません。原田マハさんがゴッホゆかりの地を歩きながら、ゴッホの世界を案内してくれるのです。
オランダで生まれたゴッホは、ロンドン、パリの画廊で働いたのち、一度は伝道師としての道を進みますが、やがて絵を描き始め、画家を目指すようになりました。そして、弟のテオから生活資金のサポートを受け、やがて画廊で働くパリのテオの元を訪れます。そして、パリで暮らし始めてから、ゴッホは画家として開花するのです。その時はまだ世の中に認められなかったのですが。
ゴッホはパリで日本の浮世絵に出会いました。色鮮やかに、見えるものを自由に描いた浮世絵。それは、きちんとした構図に基づいて描くフランスアカデミー画家の作風とは異なり、新しい作風で描く印象派に多大な影響を与えました。そして、ゴッホは日本の浮世絵に惚れ込みました。
しかし一体どうして、パリにジャポニズム、浮世絵が知られるようになったのでしょうか。そこを探った原田マハさんは、林忠正に行き着いたのです。
1867年、パリ万博で日本の美術工芸品が披露されました。その万博にフランス語の通訳として参加し、そのままパリに定住して1884年からパリで美術商の仕事を始めた人物こそが林忠正だったのです。
残念ながら林忠正の名前は、日本ではあまり知られていません。けれど、当時のヨーロッパに日本美術を広め、印象派画家たちに影響を与える機会をつくった林忠正という人物をもっと知ってもらいたい、そんな思いから『たゆたえども沈まず』の執筆に至ったとマハさんは言っています。ゴッホが弟テオを訪ねてパリに移住した年が、1886年、そして林忠正が独立して「林商店」を開いた年もまた1886年。この偶然の一致により、原田マハさんの小説『たゆたえども沈まず』が誕生したのです。
『ゴッホのあしあと』の中では、ゴッホがアルルへ移住した時の思い、ゴーギャンとの共同生活が破綻し、耳切り事件を起こした後のサン=レミでの療養生活をするゴッホ、そして最期の地であるオーヴェール=シュル=オワーズへ旅だった時のゴッホの心境などを、それぞれの場所で描かれた絵画ととともに、マハさんが語ってくれます。絵画の解説本を読むときとは違い、ストーリーがあるからこそ絵が心に響いてくるのです。
原田マハさんは、自らオーヴェール=シュル=オワーズを訪れ、ゴッホがピストルを撃った場所はここではないかという場所を見つけています。
ゴッホの死後、程なくして弟のテオもまた衰弱していき、半年後に亡くなってしまいます。
ゴッホのことを現代の私たちが詳しく知ることができるのは、2人の間で交わされた手紙が残されていたからだと言われています。テオの妻であったヨーが、手紙を大切に保管し、書簡集を出版したために、ゴッホ兄弟の人生がこうして後世に語り継がれることになったそうです。
ゴッホの死には謎が残っています。ゴッホはどこでピストルを手に入れたのでしょうか。そして、自らを撃ったピストルは、その後どこへ行ったのでしょう・・・
この謎を題材にした原田マハさんの新たな作品が、その後誕生しました。
4 原田マハ『リボルバー』
主人公はパリの大学でゴッホとゴーギャンを研究した日本人女性、冴(さえ)。博士論文に挑戦することを目標に、小さなオークションハウスで働いています。そこへ突如現れた50代と思しき女性、サラ。彼女が持ち込んだものは、錆びついたリボルバーでした。そしてサラはそれを、フィンセント・ファン・ゴッホを撃ち抜いたリボルバーだと言うのです。
冴はオークションハウスの命運をかけてリボルバーの鑑定、謎解きに取り掛かります。アムステルダムにあるファン・ゴッホ美術館、ゴッホ終焉の地となったオーヴェール=シュル=オワーズで彼が10週間を過ごした下宿屋ラヴー亭を訪問して関係者に話を聞きます。そして、ゴッホが自殺に使ったリボルバーは別のものであったという話が浮上するのです。
ゴッホのストーリーが展開されていくかに思われるこのストーリーは、それからゴーギャンのお話へと移って行きます。
アルルでいっときゴッホと共同生活を営んだゴーギャン。そのゴーギャンとゴッホの関係はどのようなものであったのでしょうか。冴とサラの会話を通してストーリーは新たに動き出します。
サラは一体何者なのか、サラが持っているリボルバーはどこから来たのか、そしてなぜサラは世界的に有名なオークション会社ではなく、わざわざ冴が働く小さなオークションハウスを訪れたのか。
読み進めていくうちに謎は深まり、そしていつの間にかゴーギャンの人生に足を踏み入れている自分に気づきました。
主人公が研究者であるだけに、事実とは違う展開を認めることはできない、そんな視点で進むこの小説は、『たゆたえども沈まず』とは違ったミステリー仕立てのアート小説になっています。そしてやはり、解説本とは違うゴッホとゴーギャンの世界が、ストーリーで体験できるのです。
***
原田マハさんはアート小説以外にもたくさんの作品を書いています。
『さいはての彼女』『ギフト』など人間の温かい気持ちが綴られている作品は、私の大好きな本の一つとなっています。
今回あげた2作の小説は、アートの知識がふんだんに盛り込まれ、その上で温かい気持ちの広がるストーリーとなっています。子供の頃からアートに親しみ、独自の思いがあるからこそできる作品なのだと実感します。
原田マハさんの作品にもっともっと触れてみようと思います。
ゴッホについて知りたい方は、こちらもどうぞご参照ください。